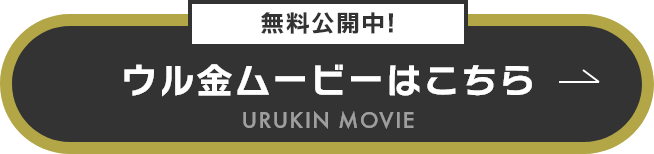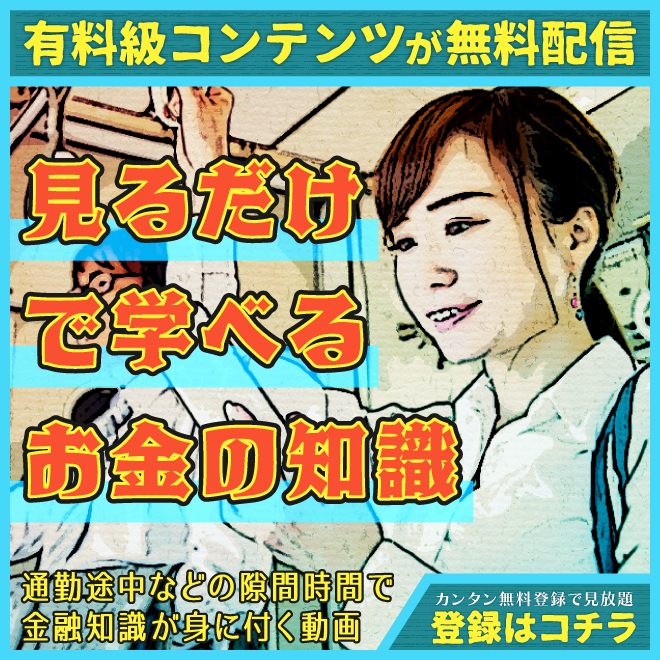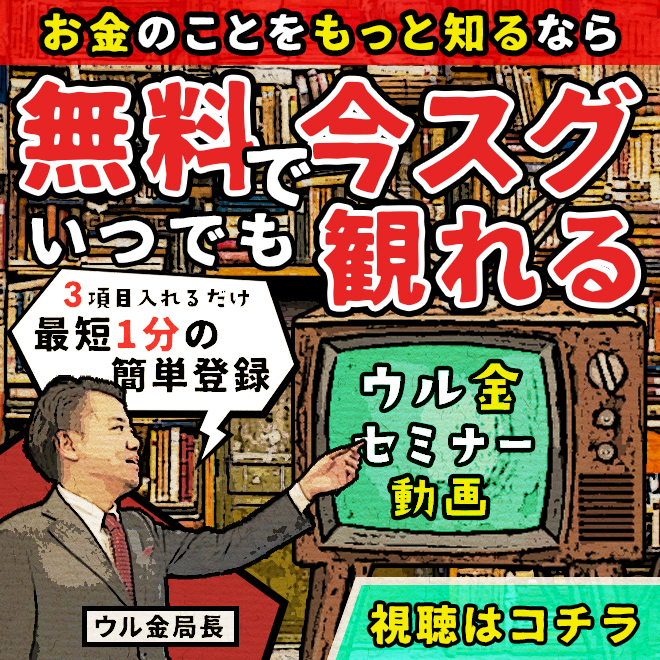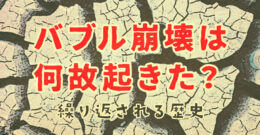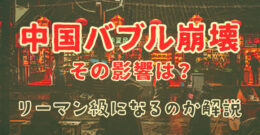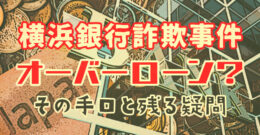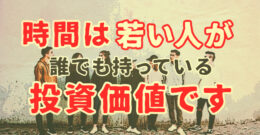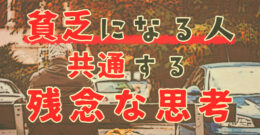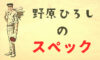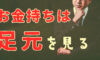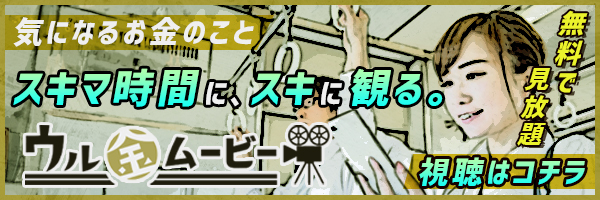公開日:
不動産
恒大集団、碧桂園デフォルトからみる中国バブル崩壊の今後
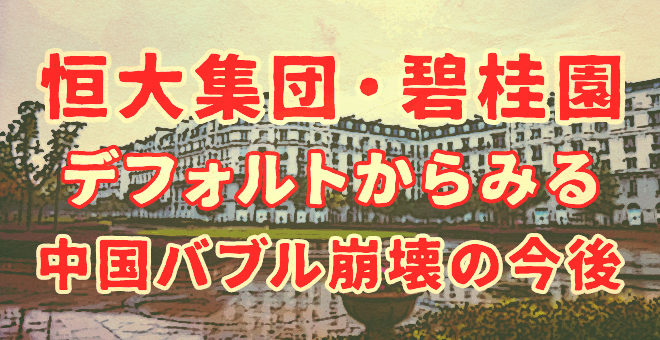
中国バブル崩壊、最早この現実は世界中の人々の中で事実となっている事かと思われます。
しかし、現実問題として恒大集団はデフォルトから2年経つ今も倒産はしておらず、債務超過している決算書が出てニューヨークで破産法の適用を申請しても倒産はしていません。
日本では支払うべきものを支払えない場合、手形の不渡りを2度出せば銀行取引が停止となり、ほぼ確実に倒産となります。
しかし、そこは中国です。
日本とは違いますから、通常のルールでは倒産となりません。
恒大集団や碧桂園といった大規模な事業者を倒産という事にしては経済への影響は計り知れません。
共産国家である中国であれば倒産させないとなればそれを実現させる事が出来てしまうようです。
しかし、強引な延命措置を取るとどういったリスクがあるのかこのコラムでは解説していきます。いえ、解説出来る程ソースが揃っていませんので考察してみたいと思います。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
倒産がもたらす影響
そもそも企業が倒産するというのはどういう事なのでしょうか?
株式会社の倒産では企業が破産申請を行うと所有している資産や債権を取引している債権者達で分配し、清算を行います。
この際、民間債務よりも税金や従業員の給与が優先されます。
通例では債務超過している企業の倒産では民間債務まで弁済されるほど資産は残らないでしょうから、単純に倒産したら返ってくるものも返ってこないと解釈して間違いではないでしょう。
企業が倒産すると取引先である銀行や、建設業者、場合によっては既存の土地所有者などの債権が未払いとなってしまいます。
恒大集団にしても碧桂園にしてもその他多くのデベロッパーでも共通する債権者がこの2つ、銀行と建設事業者です。
二次受け三次受けの建設業者では建築代金の支払いが行われず、銀行も融資した元金を回収出来ないという事になります。
建設業者では支払代金の入金が無いとなれば建築資材の支払いや人工代を支払えないとなり、連鎖的に不渡りを出す事になってしまいます。
銀行では不良債権を清算する事が出来るのでいっそ倒産した方が長く不良債権を抱えなくて済むのですが、貸し倒れが起こるのは事実ですので銀行の体力によっては屋台骨がぐらつくかもしれませんし、何より恐ろしいのがこれを切っ掛けに取り付け騒ぎが起こる事です。
取り付け騒ぎとは銀行不信から皆が銀行からお金を引き上げる事を指します。
恒大や碧桂園クラスの企業倒産ともなれば金融市場が乱れるのは必至です。
様々な憶測やニュースが飛び交う中で何のきっかけで取り付け騒ぎが起こるか分かりません。
銀行は取り付け騒ぎが起こると倒産してしまいます。
なので、銀行からすると元本が回収出来ない以上に取り付け騒ぎになる事の方が問題なのです。
事実として中国の銀行が本件の不良債権で倒産するかと言えばどこもしないでしょう。
予期せぬ倒産は取り付け騒ぎにより起こります。
中国金融業界が危惧する事態は取り付け騒ぎを引き起こしてしまう事なのです。
徳政令が可能?常識では測れない中国

しかし、中国でそうなるかはなんとも疑問です。
先ず、取り付け騒ぎは国営金融機関により抑制する事が可能だと思われます。
政府が倒産させないと言えば倒産しないという事が可能なのですから、政府広報だけでかなりの銀行不信を払拭出来るでしょう。
更に徳政令が可能であるという事も大きいです。
徳政令とは債務の免除を政府が行うもので、借金の棒引きを国がしてくれるというものです。
この徳政令が恒大集団や碧桂園に出されれば、現在の債務超過が解消されますので倒産自体を回避できます。
実際近年アメリカで学生ローンに対してこの徳政令が大統領令として使われニュースに挙がりました。
資本主義経済圏のアメリカで可能なのですから、中国なら考えられるのかもしれません。
この徳政令は諸刃の剣と言われています。
というのも、債務を免除された事業主は助かりますが、債権者である金融機関はたまったものでは無いからです。
恒大集団や碧桂園をとるか、銀行を取るか、徳政令はいずれかを選ぶ事になるのです。
それでも、検討の余地はありそうです。中国は人民元という自国通貨を持っています。
債務を免除してもそれだけ人民元を発行して金融機関に対して穴埋めする事が出来ます。
自国通貨発行でお金を供給する事はインフレに繋がると言われていますが、目下デフレ騒ぎの中国では問題にならないでしょう。
徳政令と聞くと夢物語のようにも聞こえますが、銀行の手当てが出来れば案外良い手段なのかもしれません。
日本では実現不可能な起死回生の手法ですが、マクロ的には混乱も少なく中国バブル終焉の形としては現実的な部分もあります。
ところがこの線は無いでしょう。
そもそも中国政府からすれば2020年のレッドラインの段階で不動産業界の縮小が必要であると判断しています。
その見方から考えれば今起きている不動産開発業者の状況は許容する予定であったと見る事も出来ます。
予定通りの結果が起こっているのに徳政令で現状を捻じ曲げるとは思えません。
今回のバブル崩壊で起こる不動産業者の一連のデフォルトを中国政府は許容するつもりであるというのが著者が調べた所感です。
どうなるかまでは勿論分かりませんが、如何に中国と言えども債務免除は無いでしょう。
問題が長期化する不良債権化
実際思い切った方法を取らないとなると恐らくなるであろう未来が不良債権化させて市場経済になじませる手法です。
これは一部にセーフティネットを設けて公金を注入して企業の延命措置を行います。
倒産はさせず、ゆっくりと不良債権を溶かしていくようなイメージです。
何をするかと言えば借り入れの利息だけ政府系銀行から新たな貸し付けを起こし利払いだけは回るようにします。
現在は利息支払いを猶予する事で延命を図っていますが、いつまでも続けられものではありません。
時間稼ぎをしている間に数多く抱えている仕掛在庫を処分しながら財務バランスの健全化を進めていくのです。
健全化と言っても実態はリストラであり、倒産処理をしているのと何ら変わりません。
仕掛在庫を処分して建築代金を支払った段階で超過債務だけを塩漬けのように抱える企業になっていくのです。
コロナにより世界中でゾンビ企業が問題になり日本でも事業融資の不良債権化が問題になりました。
このような活かさず殺さずの不良債権化は長く中国経済に影をもたらし、目下の長期デフレが懸念されている事態をさらに悪化させかねません。
ソフトランディングを目指した結果が最も問題の長期化に繋がるというジレンマがここにあります。
恒大集団には地元自治体から役員が就任していますし、銀行筋からも人員が送り込まれています。
これらの事からある程度政府コントロールが効く状態にあるとも見れます。
ところが、前項でも挙げた通り中国政府は現状を許容すると思われますので、最終的な救済を目指すという事は無いのではないかと著者は考えています。
とはいえ、中国経済の混乱や国民感情を鑑みると業界全体を非情にも見捨てる事は出来ないと思います。
そもそも破産処理として現在抱える不動産を処理するなんて事は不可能です。
日本で置き換えて考えると管財人を選定して不動産の処理なんて行ったらいつ終わるか分からないという事です。
破産申請→管財人選定→資産評価→債権者分配を行いますが、不動産価格の査定等どれだけ時間があっても終わらないでしょう。
だったら、多少税金を投入してでも自浄作用で処理して貰った方が早く、安く済むという事になります。
既存の事業者ネットワークを使って売却処理をした方が結果的に合理的です。
今デフォルト騒ぎになっている開発業者全ての債務を合計すると150兆円にも上ります。
そんな巨額不動産の破産処理を受け付けられるだけの弁護士も裁判所も手配出来ないでしょうし、法律に則ってなんて事になった方がよっぽど解決できないでしょう。
倒産させない方が合理的という現実の捻じれが起こってしまっているのです。
影響を大きく受けるのは金融市場

不良債権化を長期に渡って受け入れるとなるとその影響は金融市場に現れる事が予想されます。
回収される事の無い債権が金融機関に残っているというのは銀行のバランスシートに悪影響を及ぼします。
それがひいては中国のあらゆる金融商品の信用に影響するかもしれません。
国内外の投資家にとって中国の金融商品の魅力が著しく低いとなれば問題は不動産市場だけに留まらず、その他分野の商品に広がってしまいます。
不動産事業は中国のGDPを支える巨大マーケットです。
その規模はGDP比30%とも言われています。
その不動産関連の金融商品に不良債権が紛れ込んでいるとなれば、投資家は一気に離れていく事になるでしょう。
リーマンショックの二の舞はごめんだという事です。
さらに加えて不動産市場の下落は担保価値の下落を意味します。
担保価値の下落はますます不動産の売却を生み、更なる不動産価格の低下を招きます。
その影響は地価だけではなく株価にも影響するでしょう。
不動産担保の価値が下がるとなると不動産以外の追加担保を求めたりといった動きが出てきます。
企業やファンド筋銀行は融資担保に株や債権を入れている事もあるでしょうから、それらが売却されていく事となれば株式市場の低迷を招きます。
売却が増える市場では誰もが買い控えを行います。
おりしも中国経済は低迷の只中で、投資家は新たな投資先を探しています。
混乱する市場を堅実な投資家が避ける事は避けられないでしょうし、政府が何をするのか分からない現状では海外の投資家筋も中国への投資は手控えるでしょう。
つまるところ中国金融市場は全体的な低迷を迎える事になります。
それも長期間にわたって続く事が懸念されるのです。
そのトリガーになりかねないのがこの中国デベロッパーの今後と言えるのです。
今後の世界への影響は?
中国は内需の国です。
リーマンショックと違いその影響は限定的であると言われています。
実際2020年の恒大集団のデフォルトを受けても世界恐慌とは程遠い状況ではあります。
しかし、流石にデベロッパーの大手が何社も立て続けにデフォルトするなんて事態はどうでしょうか?
40兆円超の負債と言えば大事ですが、とはいえ一社の出来事です。
これを皮切りに同じように何社も数十兆の債務でデフォルトしていったらどうなる事か分かりません。
これまで躍進してきた中国のパワーに影響されて来た市場は世界中にあります。
中国経済の冷え込みがどの程度周辺国家の経済に影響を与えるのかを推定するのは困難ではあります。
しかも、その時期も中国だけに分かりません。
すぐに起こるかもしれないし、数年後になるのかもしれない。
政府の動きによって経済が大きく変わる中国です。
この恒大集団や碧桂園の問題を見守っていく事で中国経済の一端を見る事が出来る事は事実です。
頭に入れておいた方が良い事は中国政府は企業を助けはしないだろうという事(なぜなら想定していた事態なので)
自国通貨を発行出来る中国ではインフレを気にせず通貨発行する事は出来るだろうという事。
日本と違い中国は人民元を発行する事に抵抗は少ない気がしています。
やろうと思えばやれる。それが今の中国です。
10年以上少子高齢化や物価高、人件費の高騰と課題に見舞われた中国ですが、なんだかんだで経済大国です。
失われた30年、バブル崩壊、少子高齢化、製造大国の凋落と日本も長らく憂き目を見てますが、なんだかんだで大国です。
今中国のニュースを日々目にしているとバブルで膨れた経済大国があたかも失墜してしまうように映りますが、客観的な事実としては経済大国の一国に台頭してきた事です。
その事実は簡単には崩れないでしょうし、この10年以上のバブル景気によってつくられた中国の産業の残滓はそれでも世界をけん引していく一助であると思うのです。
著者の結論としては中国のバブル崩壊は今後長引く金融不況を中国にもたらすとは思います。
しかし、それが直ちに大国中国の凋落を意味するかと言えばそんな事は無いと思います。
膨れ上がったバブルは弾け、収まる所に収まる。
その収まる所はそんなに低い所では無く、これまで躍進した中国産業の多くが機能停止する事も無ければ世界の中で中国が没落するなんて事も無いと思います。
むしろ、共産国家ならではの剛腕を振るい思いもよらない解決策を見せてくれるのかもしれません。
今後の続報を注視してまた、記事にしていきたいと思います。
本記事は国外の事情につき精査された内容では無い部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。
関連記事がいくつかございますので併せてご覧下さい。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
関連記事:リーマンショックと中国バブル崩壊は何が違う?
https://urukin.com/779-2/
関連記事:エバーグランデの決算から分かる事
https://urukin.com/2219-2/
関連記事:中国で増える鬼城中国バブル崩壊の何故
https://urukin.com/792-2/
関連記事:碧桂園(カントリー・ガーデン)デフォルト、何故なのかを解説
https://urukin.com/2393-2/
この記事を書いた人

ライター
佐藤大介(さとうだいすけ)
ウルトラ金融大全局長
ウルトラ金融大全の監修を務めます。
金融リテラシーを高める為、セミナー講師として活動。
「超一流の口だけ男」と評される氏のセミナーは非常に分かりやすく、何度も受講するファンが沢山います。
リンクからウル金セミナーも是非ご覧下さい。
おすすめの記事