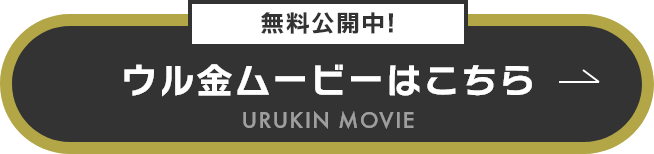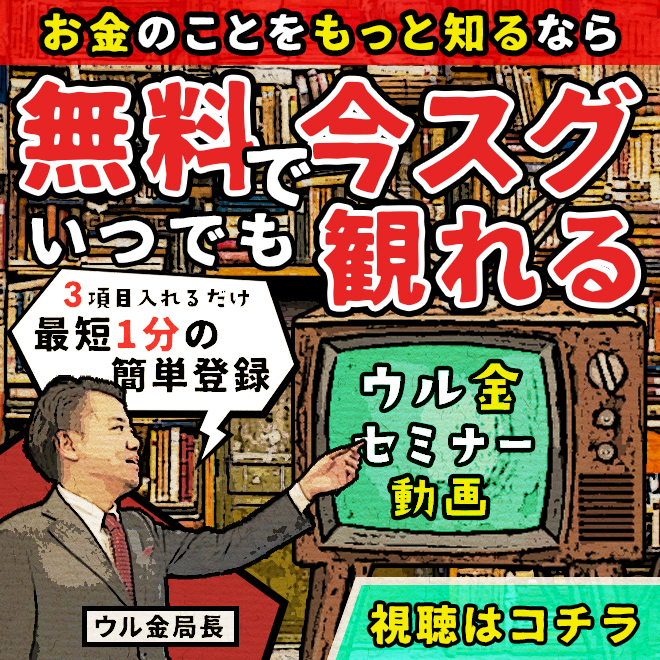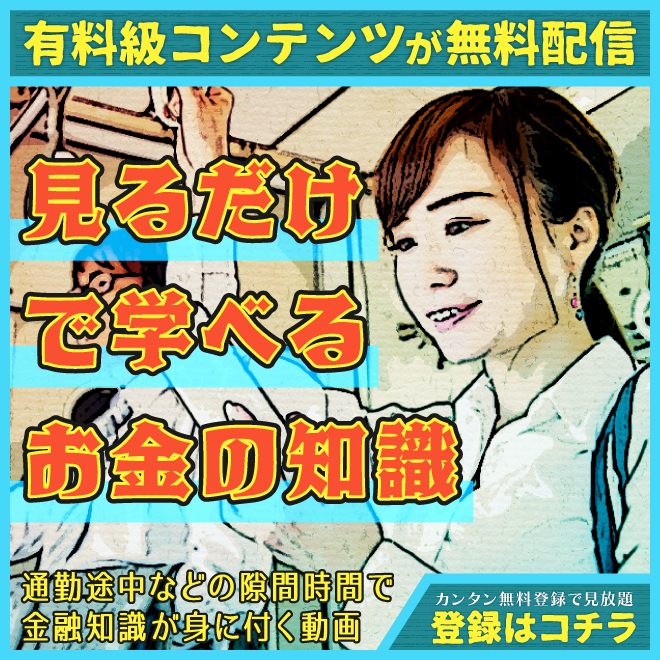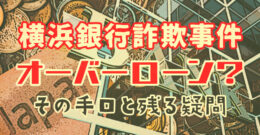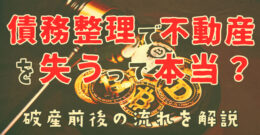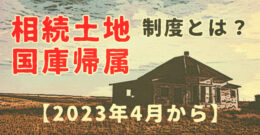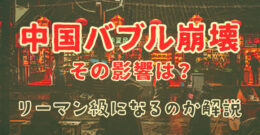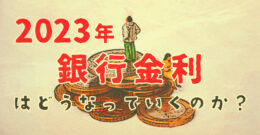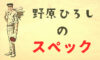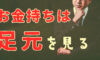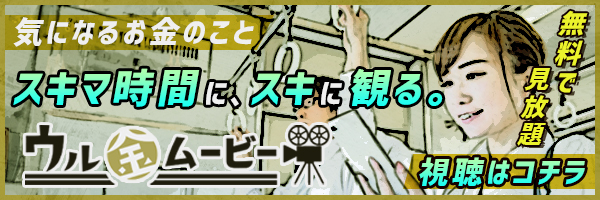公開日:
不動産
恒大集団が破産申請!中国経済の今後はどうなるか?

中国経済の先行きがかつてないほど不安定になってきています。以前から中国経済のバブルが崩壊するのではないかと懸念されていましたが、近年さらにその懸念が強まっている状況です。
本記事では、中国経済が抱える懸念材料を解説し、中国経済のバブルが崩壊した場合、日本経済にどのような影響を与えるのかをみていきます。この記事を最後までお読みいただき、中国経済の状況と将来のリスクを把握するとともに、自身でできる対策を考えていきましょう。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
中国経済の懸念材料
中国経済の懸念材料は主に次の4つが挙げられます。
・不動産問題
・デフレ問題
・失業率
・人口減少
以下で詳しくみていきましょう。
不動産問題
中国の大手不動産会社の業績が悪化しており、経営破綻が懸念されています。ロイター通信によると大手不動産会社の中国恒大集団(エバーグランデ)は8月17日、米連邦破産法15条の適用をニューヨークの連邦破産裁判所に申請しました。今後、中国本土で正式に経営破綻が発表されるかもしれません。
中国恒大集団は2021年、2022年の決算発表で、2年間で合計約5,800億元(約11兆2,000億円)の最終損益を計上したことがわかりました。これは中国企業で過去最大の赤字額です。巨額の損失を計上することとなった主な要因として、中国の人口減少や雇用不安、国民の住宅購入意欲の減退が挙げられます。
それに加えて2020年夏に不動産大手の財務状況への監視が強化されたことにより資金調達が制限され、金融機関の貸し渋りに直面します。このことで、建設の停滞を恐れた消費者は恒大が管理している物件の購入を敬遠しました。
そして、2020年12月期に5,000億元を超えていた売上高が、2022年12月期には約2,300億元まで減少し、中国恒大集団の経営が窮地に陥ったのです。
信用不安による販売不振は中国恒大集団に限りません。大手不動産会社の碧桂園(カントリー・ガーデン・ホールディングス)も巨額の損失を計上しています。碧桂園は8月10日、2023年1〜6月期の最終損益が450億〜550億元(約9000億〜1兆1000億円)の赤字に転落したと発表。同社は22年の中国不動産販売額で首位でした。
ロイター通信は8月上旬、碧桂園が米ドル建社債の利息を支払えなかったと報じています。同社は資金繰りが悪化しており、30日間の猶予までに支払いができない場合はデフォルト(債務不履行)に陥ってしまいます。
もし、中国恒大集団などの大手不動産会社が経営破綻した場合、金融機関や取引先などに大きな打撃を与えることとなるでしょう。連鎖倒産などのリスクが高まることも予想されます。その波及効果はやがて、中国経済全体に深刻な影響を与えるかもしれません。
デフレ問題
中国ではデフレ懸念も指摘されています。中国国家統計局が2023年8月9日に発表した7月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比0.3%下落。景気低迷が懸念されることから、自動車など耐久財の販売がさえない状況です。自動車やバイクが4.4%、スマートフォンなどの通信機器は2.6%下落。家具や家電は1.8%下落した模様です。
しかし、全面的に物価が下落している一方で、旅行や飲食店などのサービス業への支出はコロナ規制終了後に急増しており、これらの分野では物価が上昇しています。コロナ規制が終了したことにより、国民の移動と娯楽関連の消費が活性化したことが要因と考えられます。
特に中国では長い期間にわたり自粛が続いていたため、人々の外出や旅行への渇望が強まっており、これがサービス業における需要の急増に繋がったといえるでしょう
日本を含め、世界の多くの国はインフレが進んでいるなかで、中国ではデフレが懸念されていることに驚く人もいるかもしれません。現在中国が抱えるデフレ問題は中国特有のものです。
世界の主要国では、新型コロナウイルスの流行に伴い長らくの間、経済活動の自粛を余儀なくされていました。そして、コロナ規制が緩和され経済活動の再開に伴いインフレが進んだのです。もちろん、インフレの進行は複数の要素が影響を与えているとされています。
厳格なコロナ規制を昨年末に取りやめた中国でも、各主要国のようにインフレが進むと予想されていました。しかし、実際にはそうならなかったのです。
前述で解説したとおり、不動産市場は経営不振に陥り国民の信頼感は低下しました。国民は不動産のような高額商品の購入を控え、家具や家電製品の需要が減少します。この消費の抑制が一層進むことで市場における価格の下落、すなわち値崩れが生じることになったのです。
加えて、中国は世界の主要国よりも厳格なコロナ規制を実施しました。この厳格な規制により多くの企業が経営難に陥り倒産が相次いだ結果、失業者が増加したのです。その結果、失業した人の収入が減り、家計の消費が冷え込んでしまったこともデフレを招いている要因の1つです。
失業率の増加
中国では失業率の増加も深刻な状況に陥っています。中国国家統計局が発表した6月の若年失業率(16~24歳)は21.3%と過去最高を更新しました。5年前の2018年11月(10%)から2倍以上に増加しており、失業率は年々深刻な状況になりつつあります。
また、統計に含まない「就職活動をしていない非学生」1600万人を含めると、実際には5割近い失業率となる可能性も指摘されています。
前述のとおり、失業率が増加すると所得が低下する人が増え、消費支出が減少します。その結果、国内の経済成長が鈍化し、さらにはデフレの圧力が高まることが懸念されます。また、若年層の失業が長期化することで、社会的スキルの形成が遅れ、将来的な労働力としての資質も低下する恐れもあるのです。
人口減少
中国の国家統計局は23年1月17日、2022年末時点の人口が14億1,175万人で、前年から85万人減少したと発表しました。人口減少は1961年以来、61年ぶりとなります。出生数は956万人と前年から107万人減少。
中国では長年一人っ子政策を実施していましたが、2016年にすべての夫婦に対して第2子まで認められることになり、実質一人っ子政策は廃止となりました。しかし、それでもなお出生数は減少を続けているのです。
国連の「世界人口推移2022」では年齢人口分布も推計しています。このデータによると、中国の人口は、2030年に14億1,561万人、2040年に13億7,756万人、2050年には13億1,254万人、2100年には7億6,667万人にまで低下すると予想しています。
このとおりに人口減少が進んだ場合、国内需要の減少による経済規模の縮小や労働力不足、投資先としての魅力低下が懸念されるでしょう。こうした状況の中、中国は出生率を高める取り組みを進めています。
2021年5月31日の中国共産党中央政治局会議では、第2子までの容認を第3子まで認める方針が示されました。その他にも税収、保険、教育、住宅、就業などの支援措置を国が講じて、家庭の出産や教育にかかる経済的負担の軽減を積極的に実施すると言及しています。
バブルが崩壊した場合の日本への影響は?

ここまで、中国では経済市場に大きな懸念材料が存在していると解説しました。もし、中国のバブルが崩壊した場合、日本にも大きな影響を与えるかもしれません。
日本の輸出先1位は中国
財務省の貿易統計によると、2022年の日本の輸出額に占める中国の構成比は19.4%で、中国は日本にとって1番の輸出先です。そのため、中国のバブルが崩壊し、内需が低下してしまえば日本からの輸出が減少する可能性があります。特に日本の製造業に大きな影響を与えることになり、企業の業績悪化が懸念されるでしょう。
日本の不動産市場への影響
日本の不動産市場にも影響を及ぼす可能性があります。中国の不動産バブルが崩壊した場合、中国人による日本への不動産投資の減少が考えられます。
中国では土地の所有権がないことから、所有権が認められている日本の不動産を多く購入しています。また、日本の物件は不動産バブルの中国に比べて、割安であったことも要因の1つです。
しかし、中国の不動産バブルが崩壊することで、富裕層の資産価値が減少し、不動産投資への能力や意欲の低下が考えられます。また、バブル崩壊後は中国の不動産価格が下落していくため、日本の不動産に割安感がなくなり買い渋りが発生することも考えられます。
そうなると、日本の不動産へ投資する数が減り、不動産価格の下落が考えられます。さらに日本の金融機関も不動産価格の下落を懸念し、不動産投資に対する融資を控えることになれば、不動産購入資金を得にくくなるかもしれません。
中国政府の今後の動向に注目
中国経済の懸念材料は「不動産問題」「デフレ問題」「失業率」「人口減少」が存在し、これらが相互に影響しながら深刻な状況になりつつあります。もし、中国経済のバブルが崩壊した場合、中国と経済的に深い関わり合いがある日本への影響は避けられないでしょう。
特に、中国への輸出が多い日本の製造業や、日本の不動産市場への影響は大きいものとなるかもしれません。こうした中、中国政府も景気の安定を目指してさまざまな刺激策を講じていますが、どこまでの効果を発揮するのか慎重にみていく必要があるでしょう。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
出典
ロイター 中国恒大、米国で連邦破産法第15条の適用申請
https://jp.reuters.com/article/evergrande-chapter15-idJPKBN2ZS1MJ
日本経済新聞 不動産が中国経済の重荷に 恒大の最終赤字、2年で11兆円 冷える住宅需要、デフレリスク懸念
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72855720Z10C23A7EA2000/
日本経済新聞 中国不動産の碧桂園、最終赤字1兆円 1〜6月見通し
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM110VD0R10C23A8000000/
ロイター 中国不動産開発の碧桂園、ドル建て債2本の利払いできず
https://jp.reuters.com/article/china-property-debt-country-garden-idJPKBN2ZJ0EP
日本経済新聞 中国経済、深まるデフレ懸念 7月物価0.3%下落 2年5カ月ぶり 車やスマホ、耐久財の販売不振
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO73500250Q3A810C2EA1000/#:~:text=
日本経済新聞 中国、潜在的な若年失業率は5割弱? 増えるニート
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM207JZ0Q3A720C2000000/
JETRO 中国の人口が61年ぶりに減少、出生数は初の1,000万人割れ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/01/7fbaf27ad202344e.html
JETRO中国の人口が減少、2023年にはインドが世界首位:国連予測
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2022/db12433a352ecc90.html
JETRO 2022年の日中貿易は前年比で微減、輸出は2桁減で6年ぶりの輸入超過に
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2023/dbc3b0a5937344ad.html
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「一人っ子政策」撤廃の影響
https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2016/05/china_01.html
この記事を書いた人

ライター
辻本剛士(つじもと つよし)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員二種
独立型FPとして相談業務、執筆業務を中心に活動中。
おすすめの記事