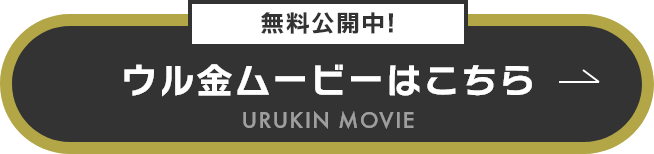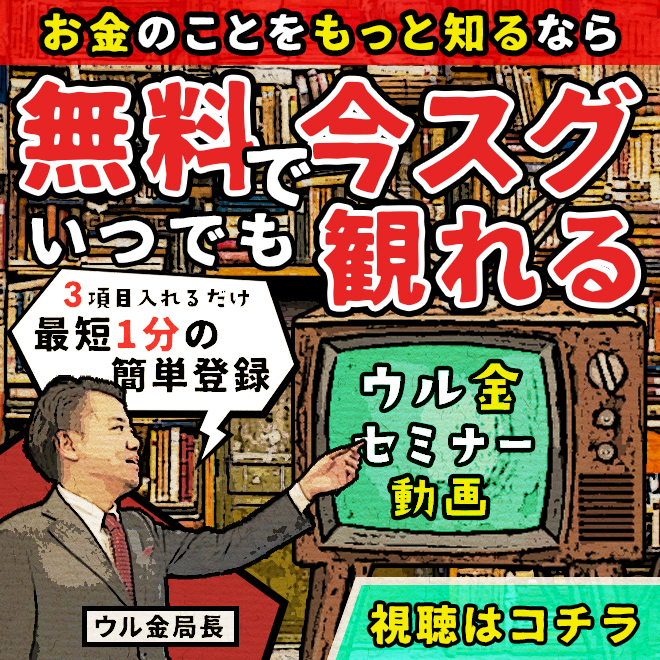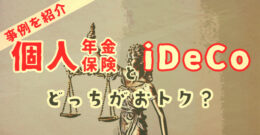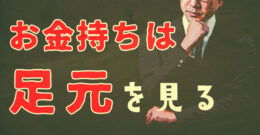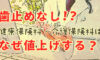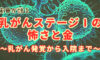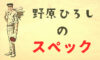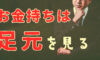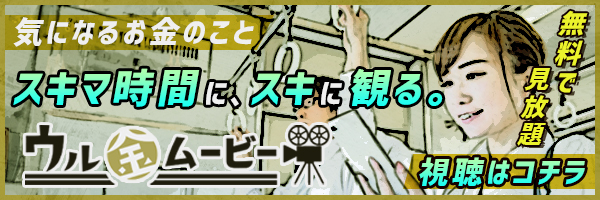公開日:
資産運用
NISAやiDeCoで銘柄選択に迷ったらインド株投信!

ここ数年でNISAやiDeCoを活用したつみたて投資が人気となっています。それらの仕組みを活用するにあたって、投資する商品を選択するのですが、種類が多くて迷ってしまうのではないでしょうか。
そんな中、今回はインド株投信を投資対象として選択することをおすすめするお話をします。現在のインドの環境は、株価がブレイクする前の日本や中国の環境に類似している点があり、その状況を重ね合わせるとインドの株価も今度、上昇が見込まれるのです。その類似した環境を精査してインド株が上昇する可能性を探っていきます。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
目次
インド株を選択すべき理由
インドは世界の中では「新興国」という位置づけになります。今後、めまぐるしい発展が見込まれる国々です。
そして、現在のインドは過去には新興国だった日本や中国の人口構成と経済成長率が類似しています。
世界を代表する経済大国に発展していった日本と中国のようにインドが発展し、それに伴い株価が上昇することが期待されているのです。
以下では、日本と中国が経済成長と株価上昇を遂げた歴史を人口構成と経済成長率を材料に見つめなおしていきます。
日本の高度経済成長と株価推移
日本の経済発展と株価推移は第二次世界大戦後に始まり、1960年代の所得倍増計画から高度経済成長を遂げて、1980年代のバブル景気まで右肩上がりの経済成長を成し遂げました。
それに伴い株価は大きな上昇を遂げていったのです。その成長をさまざまなデータと照らし合わせながら見ていきましょう。
平均年齢・生産年齢人口
平均年齢はその後の経済成長率を反映します。平均年齢が低い国は、生産年齢人口が多い国です。
生産年齢人口とは15~64歳という年齢層で、労働して給料を受け取り、その給料でさまざまなモノやサービスの消費にまわします。
この年齢層のボリュームが大きい国は経済活動が活発であり、経済成長率が高くなる傾向にあるのです。そして、国や自治体の税収も増えて、公共事業にまわす資金も多く、これも経済成長率が高くなる要因ともなるのです。
【1950年~2000年 日本の平均年齢】
|
年 |
平均年齢 |
|
1950年 |
26.6歳 |
|
1960年 |
29.0歳 |
|
1970年 |
31.5歳 |
|
1980年 |
33.9歳 |
|
1990年 |
37.6歳 |
|
2000年 |
41.4歳 |
引用:政府統計の総合窓口 平成17年度国勢調査よりhttps://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003407037
日本の平均年齢は戦後から5年後の1950年はなんと26.6歳という若さです。
その後も平均年齢は、緩やかに上昇していきます。
1950年から30年後の1980年は、7.3歳上の33.9歳に上昇します。
しかし、この上昇はその後は急激に進んでいきます。
1980年から2000年への20年間で7.5歳も上昇しており、急な高年齢化が起きていることがわかります。
【1950年~2000年 日本の生産年齢人口の推移】
|
年 |
生産年齢人口 |
全人口 |
生産年齢人口比率 |
|
1950年 |
5,017万人 |
8,411万人 |
59.6% |
|
1960年 |
6,047万人 |
9,430万人 |
64.1% |
|
1970年 |
7,212万人 |
1億466万人 |
68.9% |
|
1980年 |
7,883万人 |
1億1,699万人 |
67.4% |
|
1990年 |
8,590万人 |
1億2,328万人 |
69.7% |
|
2000年 |
8,622万人 |
1億2,670万人 |
68.1% |
引用:総務省 我が国の人口の推移https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.soumu.go.jp%2Fjohotsusintokei%2Fwhitepaper%2Fja%2Fh28%2Fexcel%2Fn1101010.xls&wdOrigin=BROWSELINK
日本の生産年齢人口と、全人口に対する生産年齢人口の推移です。おおむね全人口の3分の2ほどが生産年齢人口となります。多くの割合が経済活動の中心である生産年齢人口ということで高い経済成長となる時期でした。
経済成長率の推移
日本の戦後の経済成長率は目を見張るものがあります。世界で注目される経済発展を遂げ、1980年代にはドイツを抜き、アメリカに次いで世界第2位の経済大国へ躍り出ることになるのです。
【1953年~1998年の日本の経済成長率の推移】
|
年 |
実質経済成長率 |
名目経済成長率 |
|
1953年 |
12.7% |
6.3% |
|
1960年 |
21.4% |
13.3% |
|
1970年 |
17.9% |
10.3% |
|
1980年 |
8.4% |
2.8% |
|
1990年 |
7.5% |
5.1% |
|
1998年 |
-2.2% |
-2.5% |
引用:経済企画庁「国民経済計算年報」をもとに高度経済成長期の経済成長率 駒澤大学さんの資料よりhttps://www.komazawa-u.ac.jp/~kobamasa/lecture/japaneco/gnp/gnp1952.pdf
高度経済成長期と言われた1960~70年頃は毎年2桁の経済成長率で、すさまじい経済発展を遂げていたことがわかります。1980年~1990年は一桁成長ですが、8%や7%の成長率は実に大きい成長です。
日経平均株価の推移
株価は経済を映す鏡です。日本の株価は高度経済成長により、戦後から15年経過した1960年を基準とすると20年後の1980年には約4倍にも増えたのです。そして1989年には38,914円という歴史的な株価を付けることになります。
【1950年~2000年の日経平均株価と平均年齢・生産年齢人口比率・経済成長率の推移】
|
年 |
日経平均株価 |
平均年齢 |
生産年齢人口比率 |
名目経済成長率 |
|
1950年 ※1 |
101.91円 |
26.6歳 |
59.6% |
12.7% |
|
1960年 |
1,356.71円 |
29.0歳 |
64.1% |
21.4% |
|
1970年 |
1,987.14円 |
31.5歳 |
68.9% |
17.9% |
|
1980年 |
7,116.38円 |
33.9歳 |
67.4% |
8.4% |
|
1990年 |
23,848.71円 |
37.6歳 |
69.7% |
7.5% |
|
2000年※2 |
13,785.69円 |
41.4歳 |
67.1% |
-2.2% |
※ 日経平均株価は対象年の12月末営業日の終値※1 経済成長率は1953年※2 経済成長率は1998年
【1950年~2021年の日経平均株価チャート】

引用:日本経済新聞社 日経平均株価70年https://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/about/ourhistory/archives/nikkeiheikin.html
中国の歴史と株価推移
中国経済の今のような発展は、1978年の中国共産党大会で伝統的な経済体制を改革して、外国資本の導入を進める、いわゆる「改革開放」が発端といえるでしょう。その後、1990年に上海・深圳で証券取引所が開業され、中国は社会主義から資本主義へシフトしたように思えます。
それ以降の中国の経済発展は目を見張るものがあります。中国の改革開放以降である1980年からの統計を見ていきましょう。
1980年以降の生産年齢人口
中国の1980年以降の生産年齢人口を見ていきましょう。
【1980年~2020年 中国の生産年齢人口と総人口】
|
年 |
生産年齢人口 |
総人口 |
生産年齢人口比率 |
|
1980年 |
5億3,800万人 |
9億8,100万人 |
59,4% |
|
1990年 |
7億4,700万人 |
11億4,000万人 |
65.8% |
|
2000年 |
8億6,400万人 |
12億6,000万人 |
68.4% |
|
2010年 |
9億8,000万人 |
13億4,000万人 |
73.3% |
|
2020年 |
9億7,900万人 |
14億1,000万人 |
69.38% |
引用:GraphChart.com資料より
https://graphtochart.com/population/china-age15to64.php#license13
世界一の人口を誇る中国で生産年齢人口が1980年から30年間で1.82倍も増えることで、とてつもない経済大国が出来上がりました。
1980年以降の経済成長率
改革開放以降の中国は大きな経済発展を遂げ、経済成長率にも表れています。
【1980年代~2020年代の年平均経済成長率】
|
年代 |
経済成長率 |
|
1980年代 |
年平均9.75% |
|
1990年代 |
年平均9.98% |
|
2000年代 |
年平均10.34% |
|
2010年代 |
年平均7.67% |
|
2020年代 |
年平均4.56% |
引用:世界経済のネタ帳より
https://ecodb.net/country/CN/imf_growth.html
日本の戦後の経済成長率ほどではないですが、1980年からの約30年間は年平均10%前後と高い経済成長率を推移しています。しかし、経済の規模が大きいので金額ベースでいうと大きいものとなります。
株価推移
1990年に開所された上海証券取引所に上場している株価で構成する上海総合指数の推移を見ていきましょう。
【1991年~2020年 上海総合指数の推移】
|
年 |
株価 |
|
1991年 |
292.75 |
|
2000年 |
2,073.48 |
|
2010年 |
2,808.08 |
|
2020年 |
3,473.07 |
引用:世界経済のネタ帳より
https://ecodb.net/stock/ssec.html
1991年から2000年までの上海総合指数の上昇率が約7倍にものぼります。この間の経済成長率は年平均約10%です。2000年以降は経済成長率が年平均10%を超えていくのですが、2008年のリーマンショックで株価が世界的に落ち込んだことにより、上海総合指数も影響を受け、上昇率が鈍りました。しかし、その後再び上昇基調に転じることになりました。
【上海総合指数 2013年~2023年チャート】

引用:Yahooファイナンスより
https://finance.yahoo.co.jp/quote/000001.SS/chart?trm=10y&styl=cndl&frm=mnthly&scl=stndrd&evnts=&addIndctr=&ovrIndctr=
インドの現状と今後の推測
インドの現状と、以前の日本・中国とを比較して、今後の株価上昇を占っていきましょう。
インドの人口は2023年についに中国を抜いて世界一になる見込みです。そして、平均年齢が約28歳です。日本で平均年齢が28歳であったのは1950年代後半となります。
1950年代後半の日本の人口は約9,000万人で、その後に訪れる日本の人口のピーク時は、その1.5倍近い約1億3,000万人です。インドも今後、さらに人口増加が見込まれています。
そして日経平均株価は1950年代後半に1,200円台だったのが、20年後には7,000円台と約6倍上昇しました。インドの株価は、今後、人口増加で経済規模が大きくなる背景が確実であることを考えると、大きく上昇する可能性が期待できます。
そして、インドの生産年齢人口も総人口の増加に伴い、増加していく見込みです。今後のインドの生産年齢人口推計と、過去の中国の生産年齢人口の推移、その時期の上海総合指数の株価推移を表にまとめたので比較してみましょう。
【インドの生産年齢人口推移・推計と中国の生産年齢人口・上海総合指数の推移】
|
|
インド生産年齢人口 |
中国生産年齢人口 |
上海総合指数 |
|
2010年インド |
約7億9,000万人 |
約8億7,000万人 |
2,073.48 |
|
2020年インド |
約9億2,000万人 |
約9億9,000万人 |
2,808.08 |
|
2030年インド |
約10億3,000万人 |
約9億9,000万人 |
3,473.07 |
|
2050年インド |
約11億4,000万人 |
|
|
引用:データブック国際労働比較2017よりhttps://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2017/02/p058_t2-4.pdf
中国とインドの生産年齢人口は10年ずれでほど同じような数で推移しています。中国・上海総合指数が約1.7倍上昇したことを考えると、インドの株価も上昇が見込まれます。そして、インドの生産年齢人口はさらに2050年に向けて増加する推計が出ています。生産年齢人口が多いと経済活動が活発となり、経済成長が見込まれることから、株価上昇が期待できます。
インドの株価推移
インドの株価の重要指標というと「SENSEX指数」です。過去10年間で約3倍上昇しています。これは総人口・生産年齢人口の増加に伴い、経済活動が活発なことが反映しています。そして、インドの平均年齢が28歳と若いこと、インドの人口や生産年齢人口は今後も増加が見込めることから、日本の平均年齢が28歳だった頃と、中国の生産年齢人口が約9億人だった頃の時期と重ね合わせてみると今後のインドの株価上昇はさらに期待できます。
そして、インド株を個別で購入するのは難しいです。証券会社等金融機関では、インド株で運用する投資信託を取り揃えていますので、目論見書や運用報告書を見て検討されてみてはと思います。
【インドSENSEX指数 2013年~2023年チャート】

引用:YahooファイナンスよりムンバイSENSEX30:指数情報・推移 – Yahoo!ファイナンス
まとめ
今回は、NISAやiDeCoで銘柄選択に迷ったらインド株をおすすめというお話をしてきました。現在のインドの環境は以前の日本や中国と類似しており、両国の株価は、その類似環境後に上昇していきました。インドは現在、まさに経済が発展途上であり、今後もさらなる成長が見込めます。個別のインド株は購入が難しいので、インド株投信やインド株を一部投資対象とした投資信託への投資がよいでしょう。しかし、投資信託は元本保証ではないこと、そして、今回の推測は確定している未來ではないので将来を保証するものではありません。あくまで投資はご自身の判断でおこなってください。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
この記事を書いた人
ライター
ウルトラ金融大全編集部(うるきんへんしゅうぶ)
ウルトラ金融大全編集部です。
ウルトラ金融大全コラムの編集や記事をお届けしています。
ウル金セミナーでは詳しい解説を動画で案内しています。
そちらも是非ともご覧下さい。
おすすめの記事