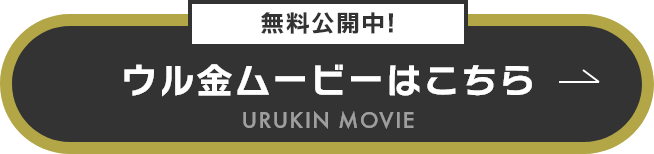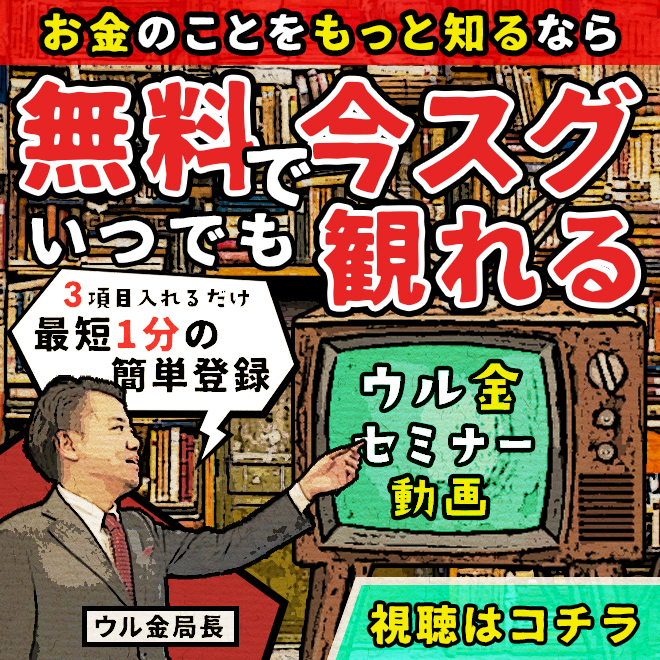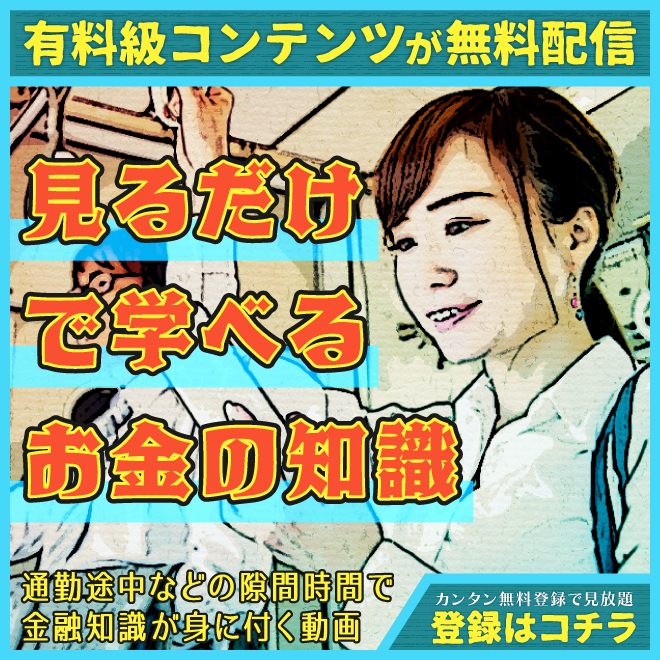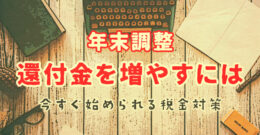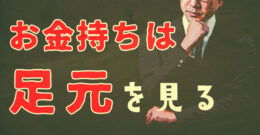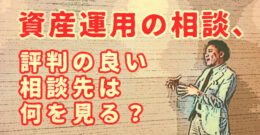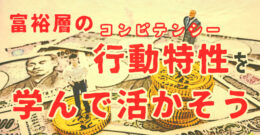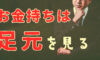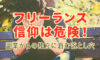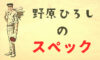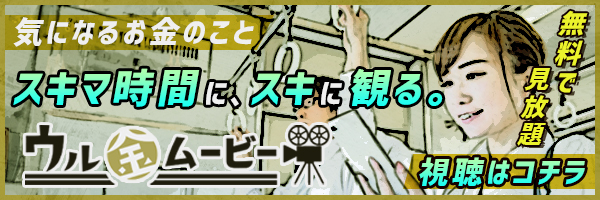公開日:
その他
宝くじの当せん金 を家族で分けたい…これって税金がかかる?
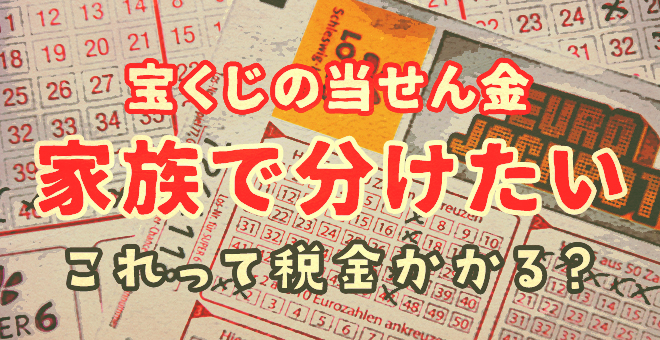
もし宝くじに当せんしたら、どのようなことに使いたいでしょうか。「車や家を購入したい」、「ゆっくり旅行に行きたい」…さまざまな夢がありますよね。中には、「両親や子供に分けたい」と考える人もいるかもしれません。
宝くじの当せん金は非課税ですが、誰かに分配するとなると税金が発生することがあるため、よく税制を理解しておく必要があります。本記事では、宝くじで発生する税金やその対策方法について解説します。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
目次
1.宝くじの当せん金は非課税
宝くじに高額当せんしたら気になるのが税金についてです。日本の所得税は累進課税制度が採用されているため、「高額当せんしても税金でほとんど持っていかれてしまうのでは?」と不安を感じる人もいるでしょう。
宝くじの当せん金には、「当せん金付証票法」という法律が定められており、その中で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と明記されています。
「所得税を課さない」ということは、つまり「所得としてみなさない」ということですので、翌年の住民税が高くなるような心配もありません。もし1億円当せんすれば、1億円をそのまま受け取ることが可能です。
2.宝くじの当せん金を分配すると税金の対象になる

宝くじの当せん金は非課税ですが、誰かに分配するときには「贈与」として贈与税が課税されるケースがあります。贈与税は、たとえ家族間であっても課税対象となりますので、「当せん金を家族で分けたい」と考えている人は注意が必要です。
ここからは、宝くじを分配するときに発生する贈与税の仕組みについて学んでいきましょう。
2-1.贈与税の税率
贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、控除額を超えた分が課税対象となります。贈与税の一般税率は下記の通りです。
【一般税率】
|
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
– |
|
300万円以下 |
15% |
10万円 |
|
400万円以下 |
20% |
25万円 |
|
600万円以下 |
30% |
65万円 |
|
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
|
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
|
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
|
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
引用:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
たとえば、宝くじの当せん金を500万円贈与した場合にかかる税金は、次のように計算されます。
|
(500万円 - 110万円) ✕ 20% - 25万円 = 53万円 |
500万円贈与した場合は53万円の税金がかかりますので、実際に手元に残るのは447万円です。
ただし、18歳以上の人が直系尊属から贈与を受ける場合は、この限りではありません。贈与税には一般税率のほかに「特例税率」があり、18歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は下記の税率が適用されます。
【特例税率】
|
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
– |
|
400万円以下 |
15% |
10万円 |
|
600万円以下 |
20% |
30万円 |
|
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
|
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
|
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
|
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
|
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
引用:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
先ほどと同じく500万円を贈与する場合でも、18歳以上の人が直系尊属から贈与する場合は、次の通りに贈与税が計算されます。
|
(500万円 - 110万円) ✕ 15% - 10万円 = 48万5,000円 |
このケースでは手元に残るのが451万5,000円となり、一般税率に比べてやや税負担が軽減されていることが分かります。
ただし、特例税率は「直系尊属から贈与される場合」に適用されるため、「配偶者の親から贈与を受ける場合」や「子供から親へ贈与する場合」は対象外となります。
2-2.贈与税をかけずに家族へ分配するためには?
前述の通り、贈与税には毎年110万円の基礎控除がありますので、110万円以内の贈与であれば基本的には贈与税の対象となりません。
そのため、「宝くじの当せん金を家族で分けたい」という場合は、毎年110万円以内で分けていくのもひとつの方法です。ただし、この暦年贈与にはいくつか注意したいポイントがあります。
暦年贈与の注意点は、本記事内の「3.暦年贈与で知っておきたい5つのポイント」でくわしく解説していますので、そちらも併せて参考にしてみてください。
2-3.共同購入した当せん金は分配可能
宝くじは「数人で共同して購入した」というケースもあるかもしれません。共同購入の場合は、参加した人それぞれに当せん金を受け取る権利がありますので、贈与税が課される心配はありません。
ただし、1人が代表して当せん金を受け取り、後から他の人へ分配した場合は、「本当に共同購入したのか」ということが分からないため、贈与税を課されてしまう心配があります。共同購入した当せん金を受け取る場合は、参加者全員で受け取りに行き、その場で分配しておくと安心です。
なお、家族に非課税で分けるために、「共同購入したことにしよう」と考える人もいるかもしれません。しかし、贈与税を逃れるための工作をすると、のちのち税務調査などを受けたときに追徴課税を受ける可能性もあります。
不要なトラブルを避けるためにも、あとから共同購入を装うようなことは控えるべきでしょう。
3.暦年贈与で知っておきたい5つのポイント

宝くじの当せん金を暦年贈与する場合は、あらかじめ次のポイントを理解しておく必要があります。
|
・贈与契約書を作成する |
ひとつずつくわしく解説していきましょう。
ポイント①贈与契約書を作成する
贈与は「あげる人」と「もらう人」の双方の同意によって成り立つため、法的には口頭での同意でも問題ありません。しかし、贈与を行った事実をきちんと残しておくためには「贈与契約書」を作成しておく方が安心です。
贈与契約書とは、「誰が誰にいついくら贈与した」という記録を残す契約書です。インターネットで検索するとひな型を見つけられますので、贈与を行う際に活用するとよいでしょう。
なお、贈与契約書は「1度作ればそれでいい」というものではなく、贈与を行う度に作成する必要があります。数回に分けて贈与を行う場合は、その都度作成するようにしてください。
ポイント②贈与の時期や金額を統一しない
先ほど、贈与は年間110万円以内であれば基本的に贈与がかからないということを説明しましたが、中には「定期贈与」とみなされるケースがあります。定期贈与とは「一定期間贈与を行うことが決まっている贈与」のことです。
たとえば、毎年100万円を10年間贈与した場合、「1,000万円を10年に分けて贈与する定期贈与である」とみなされる可能性があります。
定期贈与とならないためには、「毎年贈与する金額や時期を変える」など、「あらかじめ定期贈与することが決まっていた」と誤解を招かないための工夫が必要です。
ポイント③あえて110万円を超えて贈与する
定期贈与とみなされないためには、あえて110万円を超えて贈与する方法もあります。仮に、年間115万円の贈与を行った場合に発生する贈与税は下記の通りです。
|
(115万円 - 110万円) ✕ 10% = 5,000円 |
基礎控除の110万円を差し引くと、納める税金は5,000円となります。基礎控除から少し上回る程度の贈与であれば10%の税率で済みますので、後から追徴課税を受けるリスクに比べれば負担は小さいでしょう。
「後から定期贈与だと指摘されないか不安だ」という場合は、あえて先に納税を行っておくのもひとつの方法です。
ポイント④受け取った通帳は本人が管理する
贈与を受ける相手が未成年である場合に気をつけたいのが、通帳の管理についてです。前述の通り、贈与の成立には「双方の同意」があることが条件となります。
両親や祖父母が贈与する際、「親や祖父母が管理している子供・名義の通帳に毎年振り込んでいく」というケースが多く見られますが、このとき受け取った本人が「贈与を受けた」という自覚がなければ贈与は成り立ちません。それは、ただ単に「資産の置き場所を動かしただけ」に過ぎないためです。
したがって、子供や孫に贈与を行う場合であっても、口座の管理は本人や親権者が行い、贈与の意思を確認するようにしましょう。
ポイント⑤相続税の対象となることがある
暦年贈与を行う場合に必ず知っておきたいのが「生前贈与加算」についてです。
生前贈与加算とは、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた資産については、相続財産としてみなすというものです。仮に、被相続人が亡くなるまで毎年110万円の贈与を受けていた場合、直近3年の330万円については相続税の対象となります。
「暦年贈与なら税金がかからないと思っていたら、相続税がかかってしまった」というケースもありますので、生前贈与加算については必ず理解しておきましょう。
また、生前贈与加算については「令和5年度税制改正」において、適用期間が3年から7年へと延長されました。2024年1月1日以降に行った贈与については、生前贈与加算が7年間へと延長されるため注意が必要です。
ただし、延長された4年間で贈与を受けた資産については、総額100万円まで加算されません。
4.宝くじに当せんしたら税制についても知っておこう
宝くじに当せんしたら、一番はじめに勉強しておきたいのが税制についてです。「税制を知らなかったから」といっても、納税を免除してもらうことはできません。
特に、贈与や相続など税金と関わりが深い分野については、税制のポイントを抑え、申告漏れなどを引き起こすことがないように注意しましょう。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
この記事を書いた人
ライター
ウルトラ金融大全編集部(うるきんへんしゅうぶ)
ウルトラ金融大全編集部です。
ウルトラ金融大全コラムの編集や記事をお届けしています。
ウル金セミナーでは詳しい解説を動画で案内しています。
そちらも是非ともご覧下さい。
おすすめの記事