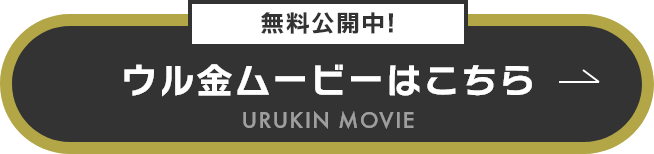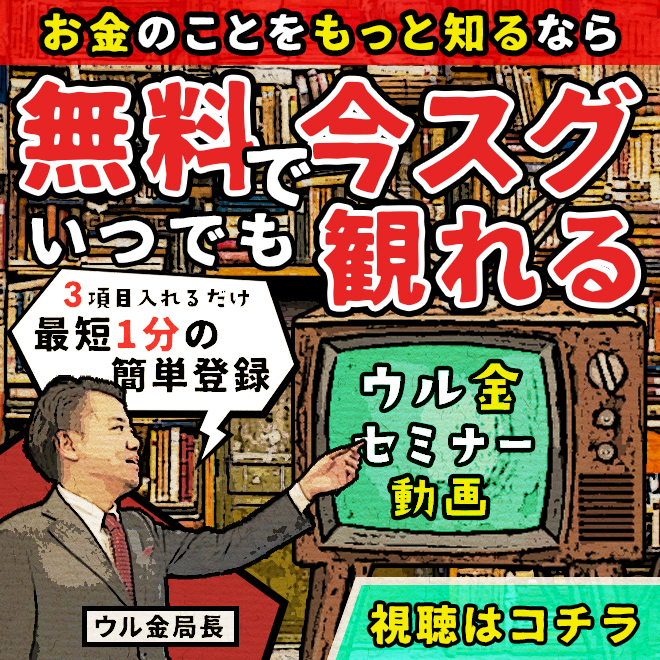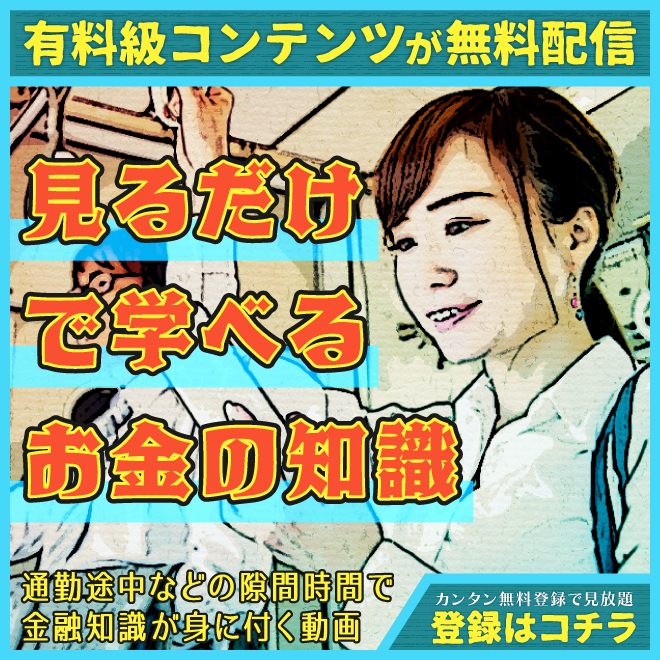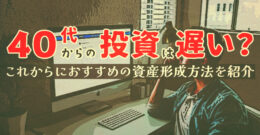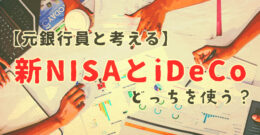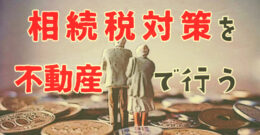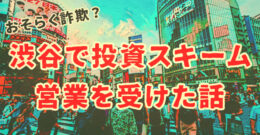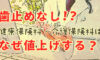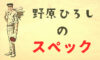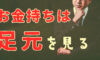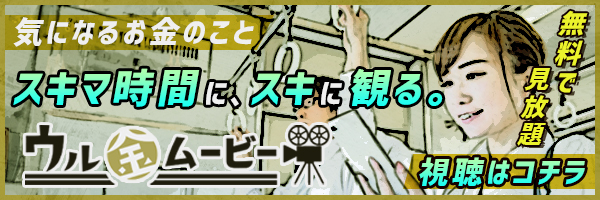公開日:
貯蓄
2024年からはじまる【新NISA】をわかりやすく解説

目次
新NISAについてわかりやすく解説

「新NISA」とは2024年から始まる新しいNISA制度です。
この制度を利用すれば年間360万円まで、最大で合計1800万円まで新NISA口座で発生する利益が非課税扱いとなります。
通常、株式や投資信託といった有価証券の場合、売買することで得られる「売却益」や、保有している株式や投資信託から得られる「配当金」、「分配金」には約20%の税金がかかります。しかし、新NISA口座であればそれが非課税となるのです。
例えば、株式に100万円投資し、価値が150万円まで上がったのでその株式を売却したとします。
本来であれば、売却によって得られた50万円の利益に対して、約20%の税金がかかり、10万円の税金を支払わなければなりません。しかし、新NISA口座の場合はこの10万円に税金はかかりません。
しかもこの新NISA制度の場合、無期限で非課税が続きます。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
新旧NISA制度の比較表

現行の「旧NISA制度」と2024年から開始される「新NISA制度」の違いを比較してみましょう。
「旧NISA制度」と「新NISA制度」について、比較表をまとめました。
図表1
| 旧NISA制度 | 新NISA制度 | |||
| つみたてNISA | NISA | つみたて枠 | 成長投資枠 | |
| 実施期間 | ~2042年末 2024年からは新規の買付不可 | 2023年末まで | 2024年1月~永続化 | |
| 制度の併用 | 併用不可 | 併用可能 | ||
| 非課税可能総額 | 800万円 | 600万円 | 1800万円(成長投資枠は1200万円まで) | |
| 年間投資上限額 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
| 投資可能期間 | 最大20年 | 最大5年 | 無期限 | |
| 取扱商品 | 投資信託 | 株式・投資信託 | 投資信託 | 株式・投資信託 |
| 非課税期間 | 20年 | 5年 | 無期限 | |
現行制度と「令和5年度税制改正大綱」をもとに筆者が作成
図表1のとおり、非課税可能総額や投資可能期間などに大きな変更がありました。
次からは新NISA制度の重要ポイントを解説していきます。
2024年から始まる新NISA制度のポイント

ここからは、新NISA制度について重要な5つのポイントを順番に解説していきます。
年間の投資上限額の引き上げ
現行の「旧NISA制度」での年間投資上限額は、一般NISAを選んだ場合は120万円、つみたてNISAを選んだ場合は40万円でした。
「新NISA制度」ではこれが360万円と大幅に拡大します。
しかし、「新NISA」では年間投資上限額360万円に対して、株式だけで年間投資上限額360万円まで買付けはできません。
360万のうち、現行の一般NISAに当たる「成長投資枠」が年間240万円まで、つみたてNISAに当たる「つみたて投資枠」が年間120万円までとなります。
つまり、株式投資へは240万円まで、残り120万円は投資信託などでつみたて運用をします。
現行の「旧NISA制度」でつみたてNISAを利用している人は、毎月およそ33333円を積み立てると年間投資上限額である40万円を使える計算です。
それが新NISA制度では、毎月10万円まで積み立てが可能。
投資額が今までの積み立て額の3倍となり、そのぶん非課税枠も増えるので、さらに節税効果が期待できるようになりました。長期で資産形成をするのに大きなメリットとなるでしょう。
制度の永続化
「旧NISA」は2023年までで制度が終了。「つみたてNISA」の場合は2042年までで終了と期間が定められていました。
しかし、「新NISA」ではこの制度が永続化されるので、自身の投資したいタイミングで始められます。
例えば、現在は育児や介護などで投資に回せる資金や時間がない人でも、制度の永続化により「新NISA」の利用開始時期を気にしないでよくなりました。
また、株式市場が下落局面で、あまり投資をしたくない期間もあるでしょう。
「新NISA」ではこのような場合も、落ち着いて株式市場が上昇局面に変わるタイミングまで取引を中断することが可能。
非課税期間が無期限
新NISAでは、非課税期間が無期限になります。
つまり、保有してから何年経過しても、非課税で運用が可能です。
通常、「旧NISA」の場合、非課税期間の5年を経過した後は売却して換金するか、保有を継続する場合は、ロールオーバーの手続きが必要でした。
ロールオーバーの制度を利用しても、非課税期間は最高で10年です。
「つみたてNISA」の場合、非課税期間である20年経過後は売却して換金するか、特定口座などに移管して保有を続けるかのどちらかです。
つまり、新NISAで最高限度額1800万円を投資している場合、そこから得られる利益は無期限で非課税となります。もし、年利(リターン)4%の場合で運用していれば、毎年72万円が非課税で受け取れます。
これが永続的に続くのは大きなメリットといえるでしょう。
生涯非課税限度額の設定
新NISAでは一生涯にわたる非課税限度額を設定することになりました。
1人あたりの非課税限度額は1800万円です。
つまり、毎年360万円を「新NISA」で買付けした場合、5年で非課税限度額の1800万円に到達します。
1800万円を超えた場合、それ以降は追加の買付けはできませんが、それでも旧NISAと比べると大幅に限度額が広がっています。
「旧NISA」の場合は、一般NISAで600万円、つみたてNISAでは800万円なので、かなりの改善になりました。
この1800万円の非課税限度額ですが、「成長投資枠」は1200万円までとなっているので注意が必要です。
例えば、「つみたて枠」を600万円まで買付けし、「成長投資枠」は1200万円までにするなどして利用できます。
売却したら非課税枠が復活
新NISAでは、非課税枠で保有している商品を売却すると、非課税枠に空きができて、その分だけ新しい商品を買付けることが可能です。
例えば、非課税枠が1800万円あり、A商品を200万円で買付けたとします。
その場合、非課税枠が残り1600万円に減少。
その後、A商品が300万円まで値上がりしたので売却しました。すると当初買付けた200万円分の非課税枠に空きがでます。
つまり、1600万円から1800万円に非課税枠が復活するのです。
現行の「旧NISA制度」にはこのような生涯限度額といった概念はなく、売却したからといって買付けた分が復活する仕組みはなかったので、この部分に関しても大きな変更があったといえるでしょう。
現在のNISA利用者はどうなる?
現時点では、「新NISA」は現在の「旧NISA制度」とは分けて管理される予定です。
現行の「旧NISA」を利用している場合でも、2024年から新しく始まる「新NISA」を利用できるので、生涯非課税限度額の1800万円からスタートできます。
例えば、2024年まで「旧NISA」を300万円利用していた場合、新NISAの最大1800万円と合わせて2100万円が非課税で運用できます。
新NISA口座はネット証券がおすすめ

いままで、金融機関に勧められて、適当にNISA口座を開設した人や、そもそも証券口座を開設したことが無い人もいると思います。
今後、新しく「新NISA口座」を開設するのであれば、ネット証券がおすすめです。
ネット証券と銀行などの金融機関では、手数料や取扱商品数などに大きな違いがあるため、後悔しないよう口座選びは慎重に行いましょう。
次はネット証券をおすすめする理由を解説していきます。
ネット証券をおすすめする理由
ネット証券をおすすめする理由は次の4つになります。
4つとも投資をするうえで、大事な要素となるのでしっかりと確認してください。
・手数料が安い
・商品数が多い
・少額から買付けできる
・ネットで簡単に買付けできる
・手数料が安い
ネット証券は銀行や店頭の証券会社より、株式や投資信託などの買付手数料が安く設定されています。
長期で資産運用をしていくなかで、手数料の差はリターンに大きな影響を与えてしまいます。
少しでも安い手数料で取引するためには、銀行や店頭の証券会社より手数料の安い「ネット証券」がおすすめです。
・商品数が多い
ネット証券の場合、投資信託の取り扱い数が2000本を超えるネット証券もあります。
分散投資をするうえで、商品の選択肢の幅が広がるのは非常に重要なことです。
・少額から買付けできる
ネット証券では、投資信託を買付ける際に100円から買付できることが多いです。
銀行や店頭の証券会社では1000円や、10000円からの買付けが多い傾向にあります。
ネット証券のように100円から買付けできれば、1000円からでも投資を始められ、なおかつ10通りに分散投資ができるので、投資初心者にとって大きなメリットといえます。
・ネットで簡単に買付けできる
ネット証券を利用すれば、ネットで簡単に買付けできるのもメリットの一つです。店頭に出向く必要もなく、自宅に居ながらでも自身の好きなタイミングで簡単に買付けができるので大変便利です。
これからは貯蓄から投資の時代へ
ここまで解説してきたとおり、新NISA制度では、いままでよりも税制面でかなりの優遇処置を受けられます。
これにより効率的に資産形成をしやすい環境がさらに整ったことになります。
円高による物価上昇や増税などで、日々の暮らしに負担が増え始めている時代だからこそ、新NISAのような制度を利用し、将来のために資産形成する必要があるのです。
まだ証券口座を開設していない人は、2024年1月から新NISAが開始されるので、それよりも前に口座開設しておくことをおすすめします。
いざ投資を始めてみたいと思っても、証券口座を開設していなければすぐに取引きできません。そうならないためにも、早めに準備しておきましょう。
出典
※金融庁 新しいNISA
※国税庁 株式・配当・利子と税
今回の記事はいかがでしょうか。お金に関する知識をもっと知りたい方は是非無料セミナーに参加してみてください。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
この記事を書いた人

ライター
辻本剛士(つじもと つよし)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員二種
独立型FPとして相談業務、執筆業務を中心に活動中。
おすすめの記事