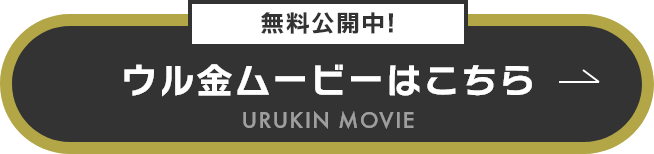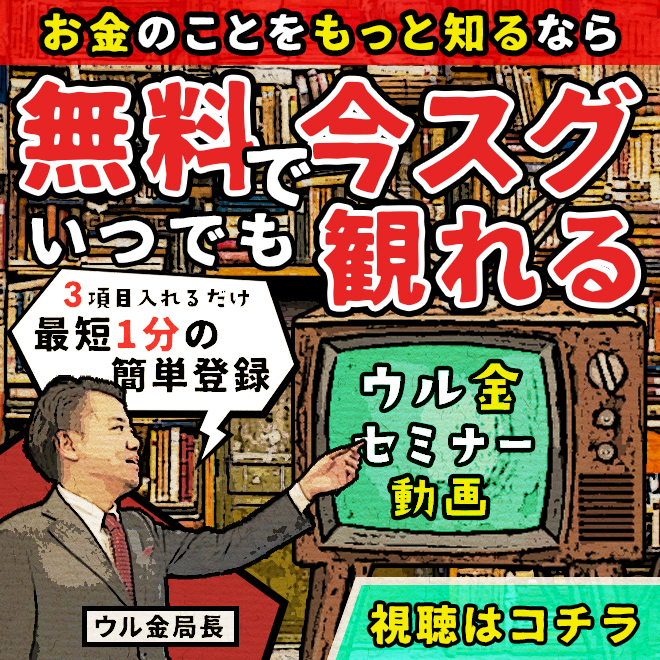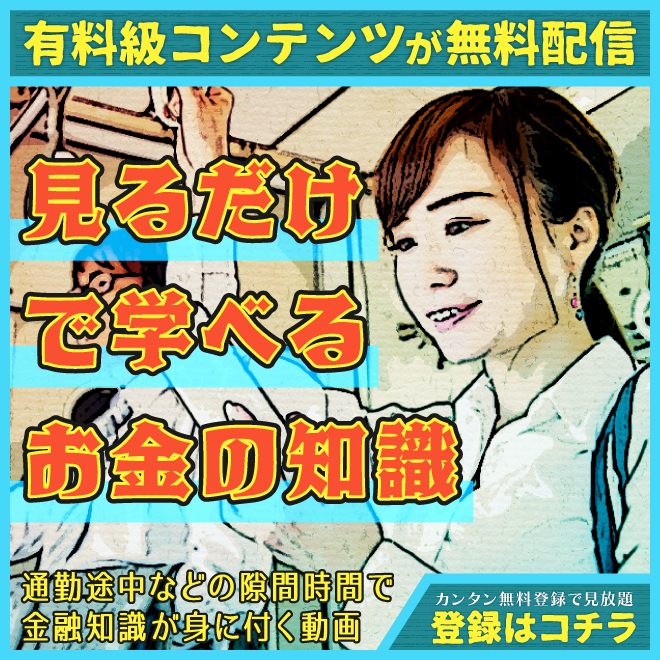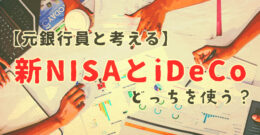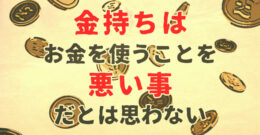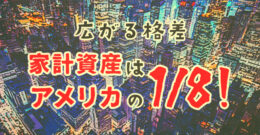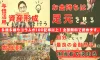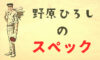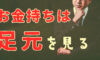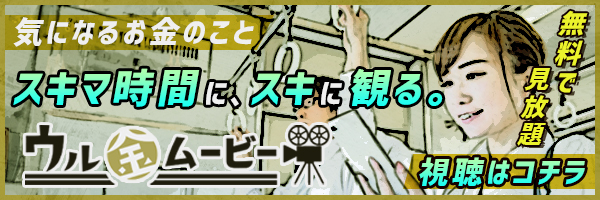公開日:
資産運用
間もなく始まる新NISA!元銀行員の使い方を紹介

2024年1月からスタートする新NISAは、投資枠が拡大し、非課税期間が無期限化されることから、現行のNISAに比べて自由度が高まります。
そのため、より制度を活用するためには、自分の投資意向に合う使い方を考えることが大切です。本記事では、元銀行員の筆者が自分の使い方を一例として紹介します。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
目次
1.新NISAの概要
まずは、新NISAの概要をおさらいしておきましょう。
|
つみたて投資枠 |
成長投資枠 |
|
|
年間投資枠 |
120万円 |
240万円 |
|
非課税期間 |
恒久化 |
|
|
非課税保有限度額 |
1,800万円(内、成長投資枠は最大1,200万円) |
|
|
対象となる金融商品 |
現行つみたてNISAと同様 |
株式、投資信託、ETF(※一部対象外あり) |
(※①整理・監理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託は除外)
新NISAの大きな変更点は次の3点です。
|
・非課税枠の拡大 |
新NISAではつみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円の投資が可能となり、計360万円の非課税投資ができるようになります。ただし、1人あたり1,800万円の限度額が定められているため、どのように1,800万円の枠を活用していくかを考えなければなりません。
また、2023年までのNISAではつみたてNISAと一般NISAの選択制でしたが、新NISAは併用ができるようになります。そのため、「リスクの小さい投資信託を積み立てながら、株式投資でスポット投資する」といった使い方も可能です。
2.元銀行員による新NISAの使い方
新NISAはより投資の自由度が高まったことから、自らよく使い方を考える必要があります。とはいえ、「どうやって使いこなせばいいのか分からない」という人も多いでしょう。
筆者は元銀行員として、NISA制度がない頃から投資信託の販売を行っていました。ここでは、そんな筆者の新NISAの使い方や投資の考え方をほんの一例として紹介します。
証券会社は変更せず
新NISAがスタートするにあたって、証券会社を変更する人も多く見られます。その理由は「より手数料が安いところがいい」、「よりポイントが貯まりやすいところがいい」といったものが多いようです。
筆者はというと、現行NISAで利用している証券会社から変更する予定はありません。というのも、証券会社のサービス改定は今後も続くことが想定されるからです。
現時点では最もサービスが充実している証券会社でも、今後もそれが続くとは限りません。ある程度顧客を囲い込んだところで、サービス内容を改定するということも十分ありえるでしょう。
つまり、「よりお得なところ」を追求するのはキリがないということです。
また筆者は、消費者として「自分が利用するサービスにはしかるべき手数料を支払いたい」という気持ちも持っています。もちろん資産運用をするにあたって、「コストを抑える」というのは大切なポイントです。
しかし、「便利なサービスを使いたい、でも手数料は支払いたくない」という消費者ばかりになると、健全な企業成長が期待できるとはいえないでしょう。
筆者はそういった気持ちから、現在利用している証券会社をそのまま新NISAでも使い続けようと考えています。
積立額は月10万円
筆者は現行NISAでは一般NISAを利用しており、月10万円ずつの積立投資を行っています。新NISAに移行後も、今のところ積立額は変更しない予定です。
積立投資ではクレジットカードで決済する「クレカ積立」を利用していますが、このクレカ積立も2024年より大きく変更される見通しです。現行NISAでは、カード会社の自主規制によりクレカ積立の上限は月5万円とされています。
しかし、新NISAで非課税投資枠が増額するにあたって内閣府令が見直されたことにより、クレカ積立は月10万円の上限へと拡大されることとなりました。
これにより、つみたて投資枠は全額クレカ積立で決済することが可能となりますので、筆者も毎月の積立投資はクレカ積立を上限まで活用する予定です。
積立銘柄は3種類
筆者は現行NISAで投資信託を4銘柄積み立てていますが、新NISAではそのうち3銘柄の積立を継続しようと考えています。それぞれ内訳と金額は次の通りです。
|
・先進国株式ファンド・・・月3万円 |
筆者はポートフォリオの半分を新興国株式にしており、リスクとしては高めの配分となっています。もちろん、今後ライフステージの変化などに合わせてポートフォリオの見直しを図る必要はありますが、現在のところは現在のバランス・金額で積み立てていく予定です。
また、現行NISAの4銘柄から新NISAでは3銘柄に減少しているのは、ある理由があります。次の章でくわしく解説していきましょう。
現在積立中の銘柄が新NISA対象とならず
新NISAの成長投資枠では、次のような条件に当てはまる投資信託は対象外となっています。
|
・信託期間が20年未満 |
これまでの一般NISAでは、こうした投資信託に関する制限はなかったため、中には「一般NISAで購入していたファンドが新NISA移行後に購入できない」というケースも想定されます。
筆者が一般NISAで購入していたファンドもこのひとつで、株式の運用に一部デリバティブ取引を用いていることから、2023年11月時点では新NISA対象ファンドとして登録されていません。
もし、今後運用方法の変更などによって新NISA対象ファンドとして登録されたら積立を再開する予定ですが、現在のところは3銘柄で積立を行っていく予定です。
なお、新NISAで対象となる投資信託については、投資信託協会のホームページで確認することができます。新NISAの成長投資枠で投資信託の購入を予定している場合は、対象ファンドとなっているか早めに確認しておきましょう。
3.こんな使い方も!新NISAの活用パターン
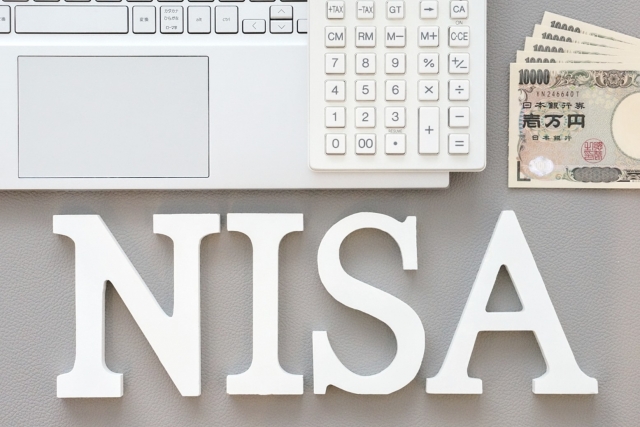
ここまで筆者の新NISAの使い方を紹介してきましたが、新NISAにはさまざまな活用方法があります。ここからは、新NISAの使い方を3パターン紹介していきましょう。
パターン①成長投資枠を配当投資で活用
新NISAの成長投資枠は上場株式も投資対象となっており、日本株だけでなく海外株式にも非課税で投資することができます。
「定期的に配当金が入る仕組みを作りたい」、「投資の楽しみが欲しい」という人は、成長投資枠で配当銘柄に投資するのもよいでしょう。
筆者も日米の配当銘柄をいくつか保有しており、新NISAでも株価が下落したタイミングなどでナンピン買いしていく予定です。
パターン②生涯投資枠のすべてを投資信託で利用
新NISAでは1人あたり1,800万円の生涯投資枠が設けられています。ただし、成長投資枠については最大1,200万円までとなっており、非課税枠すべてを使い切るためには一部投資信託を保有する必要があります。
一方、つみたて投資枠については上限額が定められていないため、1,800万円すべてを投資信託で保有することが可能です。仮につみたて投資枠を年間上限の120万円利用する場合、15年かけて生涯投資枠を埋めていく計算となります。
「個別銘柄の株式投資はハードルが高い」、「銘柄選定の手間を掛けたくない」という人は、生涯投資枠をすべて投資信託に充てるのもひとつの方法です。
パターン③iDeCoとの併用で税制メリット向上
新NISAでは非課税枠が拡大されることから、「なるべく余裕資産を資産運用に回して非課税枠を多く利用したい」と考える人もいるでしょう。しかし、より税制メリットを向上させるのであれば、iDeCoと併用することもおすすめです。
iDeCoは掛金を全額所得控除できるため、現在納めている所得税や住民税の税負担を軽減できるメリットがあります。たとえば、iDeCoに月1万円拠出する場合、年間で12万円が所得から控除される仕組みです。
筆者は、iDeCoの上限である月6万8,000円を拠出していますが、毎年確定申告のときに税制メリットの大きさを実感します。
iDeCoの拠出上限は職業や勤務先によって異なりますので、自分の上限額を確認したうえでNISAとの併用を検討してみましょう。
なお、会社員の場合は年末調整で所得控除が行えますので、原則確定申告を行う必要はありません。
4.新NISAは早く使い切るのが正義?
投資関連のネット記事やSNSでは、度々「新NISAの生涯投資枠は早めに使い切ろう」との言及を見かけることがあります。しかし、必ずしもその考え方は正解とはいえません。
仮に新NISAを毎年上限の360万円まで使い切った場合、5年で生涯投資枠を埋めてしまうこととなります。よりリスクを抑えて運用するためには、「投資するタイミングを分散すること」が大切ですが、5年間の投資では「タイミングを分散している」とは言い難いでしょう。
投資先について「これから右肩上がりに上昇していく」と確信しているのであれば、なるべく早めに生涯投資枠を埋めるのが正解かもしれません。しかし、金融市場において「必ず上昇する」というものはありませんので、リスク分散のためには「なるべく長期間かけて分散投資する」という方が安心です。
新NISA移行後は「早く生涯投資枠を使い切らなくちゃ」と焦るのではなく、「じっくり時間をかけて分散投資していこう」という気持ちを保つようにしましょう。
5.新NISAに向けて使い方を考えよう
2024年1月からスタートする新NISAをより上手に活用するためには、自分の投資意向を明確にしておく必要があります。投資意向が明確になっていなければ、適切な投資先や投資方法を選べないためです。
新NISAへ移行するにあたって、改めて「何のために投資するのか」、「どれくらいのリスクを許容できるか」といったことを振り返ってみましょう。
ウルトラ金融大全が動画で見れる!
お金の事が分かる!増やせる!無料動画が公開中!
この記事を書いた人

ライター
椿 慧理(つばき えり)
銀行を10年間勤務し経験を通じて得た金融知識を活かし、金融ライターとして独立。
金融商品やマーケットの解説、税制解説など初心者にも分かりやすい記事を手掛ける。
自らも12年の投資経験を持ち、国内外株式、投資信託、暗号資産を運用中。
保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種、内部管理責任者
おすすめの記事